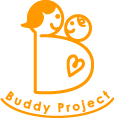2007年03月21日
小児科受診の注意点
乳幼児健診、予防接種、発熱など体調の変化の際に、受診している「小児科かかりつけ医」は、子供の具合が悪い時だけでなく、健康な時の様子も知っているため、子供の状態を判断しやすい利点があります。赤ちゃんから思春期ころまでのお付き合いの中で、親と一緒に子供の成長に立会ってくれる存在であり、子供にとっては、関わってくれる安心できる大人の一人として、役割を担っています。同時に、親の成長にも立会ってくれる存在でもあります。
小児科かかりつけ医は、何科の医師が診察するのが適切かを診立て、他の科の専門医への橋渡しもします。
また、小児科の領域の病気も多種多様で、子供の状態によっては別の医療機関や別の医師の診立てや治療が必要なこともあり、紹介先にそれまでの経過を申し送りします。
小児科受診のこつは以下の通りです。
■必ず必要なもの(保険証、乳幼児医療証、母子手帳、お薬手帳)を忘れないこと。
■いつから、どのようなことが心配か(機嫌、お乳の飲み・食欲、睡眠はどうか)を要領よく説明すること。メモなどをつくるのも良いでしょう。発熱があれば、熱型表(体温記録表)なども持参し、前医があれば必ず伝えること。
■医師の診立てと治療方針のほかに、家庭でのお世話のポイント(何に気をつければ良いのかなど)についても聞いておくこと。
■次回受診の必要な場合は、その時期も聞いておくこと。
小児科かかりつけ医は、何科の医師が診察するのが適切かを診立て、他の科の専門医への橋渡しもします。
また、小児科の領域の病気も多種多様で、子供の状態によっては別の医療機関や別の医師の診立てや治療が必要なこともあり、紹介先にそれまでの経過を申し送りします。
小児科受診のこつは以下の通りです。
■必ず必要なもの(保険証、乳幼児医療証、母子手帳、お薬手帳)を忘れないこと。
■いつから、どのようなことが心配か(機嫌、お乳の飲み・食欲、睡眠はどうか)を要領よく説明すること。メモなどをつくるのも良いでしょう。発熱があれば、熱型表(体温記録表)なども持参し、前医があれば必ず伝えること。
■医師の診立てと治療方針のほかに、家庭でのお世話のポイント(何に気をつければ良いのかなど)についても聞いておくこと。
■次回受診の必要な場合は、その時期も聞いておくこと。
Posted by mamabuddy at
03:12
│Comments(0)
2007年03月21日
小児科受診の注意点
乳幼児健診、予防接種、発熱など体調の変化の際に、受診している「小児科かかりつけ医」は、子供の具合が悪い時だけでなく、健康な時の様子も知っているため、子供の状態を判断しやすい利点があります。赤ちゃんから思春期ころまでのお付き合いの中で、親と一緒に子供の成長に立会ってくれる存在であり、子供にとっては、関わってくれる安心できる大人の一人として、役割を担っています。同時に、親の成長にも立会ってくれる存在でもあります。
小児科かかりつけ医は、何科の医師が診察するのが適切かを診立て、他の科の専門医への橋渡しもします。
また、小児科の領域の病気も多種多様で、子供の状態によっては別の医療機関や別の医師の診立てや治療が必要なこともあり、紹介先にそれまでの経過を申し送りします。
小児科受診のこつは以下の通りです。
■必ず必要なもの(保険証、乳幼児医療証、母子手帳、お薬手帳)を忘れないこと。
■いつから、どのようなことが心配か(機嫌、お乳の飲み・食欲、睡眠はどうか)を要領よく説明すること。メモなどをつくるのも良いでしょう。発熱があれば、熱型表(体温記録表)なども持参し、前医があれば必ず伝えること。
■医師の診立てと治療方針のほかに、家庭でのお世話のポイント(何に気をつければ良いのかなど)についても聞いておくこと。
■次回受診の必要な場合は、その時期も聞いておくこと。
小児科かかりつけ医は、何科の医師が診察するのが適切かを診立て、他の科の専門医への橋渡しもします。
また、小児科の領域の病気も多種多様で、子供の状態によっては別の医療機関や別の医師の診立てや治療が必要なこともあり、紹介先にそれまでの経過を申し送りします。
小児科受診のこつは以下の通りです。
■必ず必要なもの(保険証、乳幼児医療証、母子手帳、お薬手帳)を忘れないこと。
■いつから、どのようなことが心配か(機嫌、お乳の飲み・食欲、睡眠はどうか)を要領よく説明すること。メモなどをつくるのも良いでしょう。発熱があれば、熱型表(体温記録表)なども持参し、前医があれば必ず伝えること。
■医師の診立てと治療方針のほかに、家庭でのお世話のポイント(何に気をつければ良いのかなど)についても聞いておくこと。
■次回受診の必要な場合は、その時期も聞いておくこと。
Posted by mamabuddy at
03:12
│Comments(0)
2007年03月21日
身体の成長ポイント(成長曲線・疾患など)
生後1ヶ月から3ヶ月までは、赤ちゃん時代の中でいちばんの発育盛りです。
体重は、たいていの子が一日平均30~40g程度増加します。身長は、1ヶ月に3~4cm程度増加します。身体は、肉付きがよくなり、肌の張りも増して、いかにも赤ちゃんらしい感じになってきます。
生まれて1ヶ月くらいは、赤ちゃんにとって胎内から胎外への生活に大転換をしなければならない時期なので、何かと異常をおこしやすい時でもあります。次のようは異常がみられた場合は、医師に診せなければなりません。
■チアノーゼ(唇、顔、からだが紫~青黒くなる)
■顔色が白く、からだが冷たくなって元に戻らない。
■息が苦しそう
■ひきつけ(けいれん)
■吐き続ける
■大量の血便
■黄疸が強い
1ヶ月を過ぎると、死んでしまうほどの異常はほとんどクリアしているので、あまり神経をとがらせる必要はありませんが、次のような場合は早めに医師に相談しましょう。
■黄疸が強く、うすくならない。
■おっぱいの飲みが弱々しく、極端に発育が悪い。
■からだの動きが変。(手足の動きがぎこちない・ぐにゃっとしてほとんど動かないなど)
■頭だけどんどん大きくなる。
3ヶ月を過ぎると、発育のスピードはこれまでに比べて鈍ってきます。この時期、今まで小さかった子が急に大きくなったり、逆に大きかった子が並に近づくなど、さまざまなパターンが見られます。赤ちゃんが元気で、極端にやせていたり太っていたりしなければ大丈夫です。体型には個人差があるからです。
ただし、元気がなかったり、体重の増加が極めて鈍い場合などは、医師に診てもらう必要があります。
体重は、たいていの子が一日平均30~40g程度増加します。身長は、1ヶ月に3~4cm程度増加します。身体は、肉付きがよくなり、肌の張りも増して、いかにも赤ちゃんらしい感じになってきます。
生まれて1ヶ月くらいは、赤ちゃんにとって胎内から胎外への生活に大転換をしなければならない時期なので、何かと異常をおこしやすい時でもあります。次のようは異常がみられた場合は、医師に診せなければなりません。
■チアノーゼ(唇、顔、からだが紫~青黒くなる)
■顔色が白く、からだが冷たくなって元に戻らない。
■息が苦しそう
■ひきつけ(けいれん)
■吐き続ける
■大量の血便
■黄疸が強い
1ヶ月を過ぎると、死んでしまうほどの異常はほとんどクリアしているので、あまり神経をとがらせる必要はありませんが、次のような場合は早めに医師に相談しましょう。
■黄疸が強く、うすくならない。
■おっぱいの飲みが弱々しく、極端に発育が悪い。
■からだの動きが変。(手足の動きがぎこちない・ぐにゃっとしてほとんど動かないなど)
■頭だけどんどん大きくなる。
3ヶ月を過ぎると、発育のスピードはこれまでに比べて鈍ってきます。この時期、今まで小さかった子が急に大きくなったり、逆に大きかった子が並に近づくなど、さまざまなパターンが見られます。赤ちゃんが元気で、極端にやせていたり太っていたりしなければ大丈夫です。体型には個人差があるからです。
ただし、元気がなかったり、体重の増加が極めて鈍い場合などは、医師に診てもらう必要があります。
Posted by mamabuddy at
03:09
│Comments(0)
2007年03月21日
身体の成長ポイント(成長曲線・疾患など)
生後1ヶ月から3ヶ月までは、赤ちゃん時代の中でいちばんの発育盛りです。
体重は、たいていの子が一日平均30~40g程度増加します。身長は、1ヶ月に3~4cm程度増加します。身体は、肉付きがよくなり、肌の張りも増して、いかにも赤ちゃんらしい感じになってきます。
生まれて1ヶ月くらいは、赤ちゃんにとって胎内から胎外への生活に大転換をしなければならない時期なので、何かと異常をおこしやすい時でもあります。次のようは異常がみられた場合は、医師に診せなければなりません。
■チアノーゼ(唇、顔、からだが紫~青黒くなる)
■顔色が白く、からだが冷たくなって元に戻らない。
■息が苦しそう
■ひきつけ(けいれん)
■吐き続ける
■大量の血便
■黄疸が強い
1ヶ月を過ぎると、死んでしまうほどの異常はほとんどクリアしているので、あまり神経をとがらせる必要はありませんが、次のような場合は早めに医師に相談しましょう。
■黄疸が強く、うすくならない。
■おっぱいの飲みが弱々しく、極端に発育が悪い。
■からだの動きが変。(手足の動きがぎこちない・ぐにゃっとしてほとんど動かないなど)
■頭だけどんどん大きくなる。
3ヶ月を過ぎると、発育のスピードはこれまでに比べて鈍ってきます。この時期、今まで小さかった子が急に大きくなったり、逆に大きかった子が並に近づくなど、さまざまなパターンが見られます。赤ちゃんが元気で、極端にやせていたり太っていたりしなければ大丈夫です。体型には個人差があるからです。
ただし、元気がなかったり、体重の増加が極めて鈍い場合などは、医師に診てもらう必要があります。
体重は、たいていの子が一日平均30~40g程度増加します。身長は、1ヶ月に3~4cm程度増加します。身体は、肉付きがよくなり、肌の張りも増して、いかにも赤ちゃんらしい感じになってきます。
生まれて1ヶ月くらいは、赤ちゃんにとって胎内から胎外への生活に大転換をしなければならない時期なので、何かと異常をおこしやすい時でもあります。次のようは異常がみられた場合は、医師に診せなければなりません。
■チアノーゼ(唇、顔、からだが紫~青黒くなる)
■顔色が白く、からだが冷たくなって元に戻らない。
■息が苦しそう
■ひきつけ(けいれん)
■吐き続ける
■大量の血便
■黄疸が強い
1ヶ月を過ぎると、死んでしまうほどの異常はほとんどクリアしているので、あまり神経をとがらせる必要はありませんが、次のような場合は早めに医師に相談しましょう。
■黄疸が強く、うすくならない。
■おっぱいの飲みが弱々しく、極端に発育が悪い。
■からだの動きが変。(手足の動きがぎこちない・ぐにゃっとしてほとんど動かないなど)
■頭だけどんどん大きくなる。
3ヶ月を過ぎると、発育のスピードはこれまでに比べて鈍ってきます。この時期、今まで小さかった子が急に大きくなったり、逆に大きかった子が並に近づくなど、さまざまなパターンが見られます。赤ちゃんが元気で、極端にやせていたり太っていたりしなければ大丈夫です。体型には個人差があるからです。
ただし、元気がなかったり、体重の増加が極めて鈍い場合などは、医師に診てもらう必要があります。
Posted by mamabuddy at
03:09
│Comments(0)
2007年03月21日
心の成長ポイント(成長過程など)
生後1ヶ月から3ヶ月の間は、眠っている時と目覚めている時との違いがはっきりしてくる時期です。目覚めている時には、動きが活発になり、まわりの人やものへの関心を示すようになります。見ることと聞くことが連動してきて、声をかけてあやせば良く笑うようになってきます。
3ヶ月を過ぎると、ほとんどの子が日中の大半を目覚めて過ごすようになるので、外からの刺激を受け止め、自分から周囲に関心を寄せる時間が長くなります。自分と周囲のかかわりを意識し、いろいろな「もの」や「こと」に気付きはじめます。その「気付き」に対し、目や手を動かし、耳を傾け、さらに新しい気付きがもたらされます。そうして次第に、気付いた「もの」や「こと」が存在感を増していくことになります。関心のある事柄には執着が生まれ、何かを長いあいだ目で追い続けたり、握りしめて離さなくなることもあるでしょう。このような時、赤ちゃんは同時に自分自身の存在に気付き、確かめているのではないでしょうか。
その後、からだ全体の動きが自由になっていくにつれて、気付き・発見が増えて、成長速度は非常に速くなります。手や口を使って、好奇心のもとに日々周りの世界を発見し学んでいくでしょう。
3ヶ月を過ぎると、ほとんどの子が日中の大半を目覚めて過ごすようになるので、外からの刺激を受け止め、自分から周囲に関心を寄せる時間が長くなります。自分と周囲のかかわりを意識し、いろいろな「もの」や「こと」に気付きはじめます。その「気付き」に対し、目や手を動かし、耳を傾け、さらに新しい気付きがもたらされます。そうして次第に、気付いた「もの」や「こと」が存在感を増していくことになります。関心のある事柄には執着が生まれ、何かを長いあいだ目で追い続けたり、握りしめて離さなくなることもあるでしょう。このような時、赤ちゃんは同時に自分自身の存在に気付き、確かめているのではないでしょうか。
その後、からだ全体の動きが自由になっていくにつれて、気付き・発見が増えて、成長速度は非常に速くなります。手や口を使って、好奇心のもとに日々周りの世界を発見し学んでいくでしょう。
Posted by mamabuddy at
03:06
│Comments(0)
2007年03月21日
心の成長ポイント(成長過程など)
生後1ヶ月から3ヶ月の間は、眠っている時と目覚めている時との違いがはっきりしてくる時期です。目覚めている時には、動きが活発になり、まわりの人やものへの関心を示すようになります。見ることと聞くことが連動してきて、声をかけてあやせば良く笑うようになってきます。
3ヶ月を過ぎると、ほとんどの子が日中の大半を目覚めて過ごすようになるので、外からの刺激を受け止め、自分から周囲に関心を寄せる時間が長くなります。自分と周囲のかかわりを意識し、いろいろな「もの」や「こと」に気付きはじめます。その「気付き」に対し、目や手を動かし、耳を傾け、さらに新しい気付きがもたらされます。そうして次第に、気付いた「もの」や「こと」が存在感を増していくことになります。関心のある事柄には執着が生まれ、何かを長いあいだ目で追い続けたり、握りしめて離さなくなることもあるでしょう。このような時、赤ちゃんは同時に自分自身の存在に気付き、確かめているのではないでしょうか。
その後、からだ全体の動きが自由になっていくにつれて、気付き・発見が増えて、成長速度は非常に速くなります。手や口を使って、好奇心のもとに日々周りの世界を発見し学んでいくでしょう。
3ヶ月を過ぎると、ほとんどの子が日中の大半を目覚めて過ごすようになるので、外からの刺激を受け止め、自分から周囲に関心を寄せる時間が長くなります。自分と周囲のかかわりを意識し、いろいろな「もの」や「こと」に気付きはじめます。その「気付き」に対し、目や手を動かし、耳を傾け、さらに新しい気付きがもたらされます。そうして次第に、気付いた「もの」や「こと」が存在感を増していくことになります。関心のある事柄には執着が生まれ、何かを長いあいだ目で追い続けたり、握りしめて離さなくなることもあるでしょう。このような時、赤ちゃんは同時に自分自身の存在に気付き、確かめているのではないでしょうか。
その後、からだ全体の動きが自由になっていくにつれて、気付き・発見が増えて、成長速度は非常に速くなります。手や口を使って、好奇心のもとに日々周りの世界を発見し学んでいくでしょう。
Posted by mamabuddy at
03:06
│Comments(0)
2007年03月21日
どうして泣くの?(不快状況・不安・便秘・睡眠など)
自分で何もできない赤ちゃんは、泣くことでママに何かを伝えようとしています。赤ちゃんが何をしてほしいのか、泣いている理由を考えてみましょう。
■不快状況
生まれたばかりの赤ちゃんが泣きだす場合、考えられる理由は主に、おっぱいの不足、おむつの不快、湿疹などのかゆみ、暑さ・寒さ、衣類の不快(窮屈・しわなど)です。
このような不快がないか調べてあげましょう。
■不安
生後1ヶ月を過ぎると、心も成長し、泣く理由も高度になっていきます。例えば、 なれない環境、人見知り、ママがいない、嫌いな音がする、などの理由で赤ちゃんは不安を感じて泣きます。また、その他の心理的な原因(イライラや遊んでほしいなど)で泣くこともあります。心理的な理由で泣いいてる場合の対処方法は、赤ちゃんによって違うので、いろいろ試してそれぞれの赤ちゃんに合ったあやし方を見つけてください。
■便秘
排便には個人差があり、毎日排便のある赤ちゃんもいれば、2~3日出ない赤ちゃんもいます。便秘になると、赤ちゃんがぐずったり不機嫌になるのですぐに解ります。
お風呂上がりにおなかを時計回りにマッサージしてみましょう。マッサージで効果がなければ、綿棒浣腸という方法もあります。綿棒にベビーオイルやグリセリンを浸し、赤ちゃんの肛門を刺激します。ただし、自分で排便できるようにするために、綿棒浣腸はあまり行わないようにします。
■睡眠
夜中に1回や2回赤ちゃんが泣くことは避けられないものです。しかし、一晩に3.4回以上泣いたり、1~2時間間隔で泣くような夜泣きぐせをおこす赤ちゃんも少なくありません。睡眠を妨げる原因がないかチェックしてください。
部屋と布団の温度、おむつ、衣服(窮屈・しわなど)、ベッド(狭くないか)、姿勢(好きな姿勢があります)、かゆみ、痛みなど。
これらに対応しても夜泣きがおさまらなければ、きっとその子は根っからエネルギーの強い子なのだと思われます。
添い寝をするか、できるだけママのそばに寝かせ、ぐずり始めたらすぐになだめられるようにすると良いでしょう。
■不快状況
生まれたばかりの赤ちゃんが泣きだす場合、考えられる理由は主に、おっぱいの不足、おむつの不快、湿疹などのかゆみ、暑さ・寒さ、衣類の不快(窮屈・しわなど)です。
このような不快がないか調べてあげましょう。
■不安
生後1ヶ月を過ぎると、心も成長し、泣く理由も高度になっていきます。例えば、 なれない環境、人見知り、ママがいない、嫌いな音がする、などの理由で赤ちゃんは不安を感じて泣きます。また、その他の心理的な原因(イライラや遊んでほしいなど)で泣くこともあります。心理的な理由で泣いいてる場合の対処方法は、赤ちゃんによって違うので、いろいろ試してそれぞれの赤ちゃんに合ったあやし方を見つけてください。
■便秘
排便には個人差があり、毎日排便のある赤ちゃんもいれば、2~3日出ない赤ちゃんもいます。便秘になると、赤ちゃんがぐずったり不機嫌になるのですぐに解ります。
お風呂上がりにおなかを時計回りにマッサージしてみましょう。マッサージで効果がなければ、綿棒浣腸という方法もあります。綿棒にベビーオイルやグリセリンを浸し、赤ちゃんの肛門を刺激します。ただし、自分で排便できるようにするために、綿棒浣腸はあまり行わないようにします。
■睡眠
夜中に1回や2回赤ちゃんが泣くことは避けられないものです。しかし、一晩に3.4回以上泣いたり、1~2時間間隔で泣くような夜泣きぐせをおこす赤ちゃんも少なくありません。睡眠を妨げる原因がないかチェックしてください。
部屋と布団の温度、おむつ、衣服(窮屈・しわなど)、ベッド(狭くないか)、姿勢(好きな姿勢があります)、かゆみ、痛みなど。
これらに対応しても夜泣きがおさまらなければ、きっとその子は根っからエネルギーの強い子なのだと思われます。
添い寝をするか、できるだけママのそばに寝かせ、ぐずり始めたらすぐになだめられるようにすると良いでしょう。
Posted by mamabuddy at
03:04
│Comments(0)
2007年03月21日
どうして泣くの?(不快状況・不安・便秘・睡眠など)
自分で何もできない赤ちゃんは、泣くことでママに何かを伝えようとしています。赤ちゃんが何をしてほしいのか、泣いている理由を考えてみましょう。
■不快状況
生まれたばかりの赤ちゃんが泣きだす場合、考えられる理由は主に、おっぱいの不足、おむつの不快、湿疹などのかゆみ、暑さ・寒さ、衣類の不快(窮屈・しわなど)です。
このような不快がないか調べてあげましょう。
■不安
生後1ヶ月を過ぎると、心も成長し、泣く理由も高度になっていきます。例えば、 なれない環境、人見知り、ママがいない、嫌いな音がする、などの理由で赤ちゃんは不安を感じて泣きます。また、その他の心理的な原因(イライラや遊んでほしいなど)で泣くこともあります。心理的な理由で泣いいてる場合の対処方法は、赤ちゃんによって違うので、いろいろ試してそれぞれの赤ちゃんに合ったあやし方を見つけてください。
■便秘
排便には個人差があり、毎日排便のある赤ちゃんもいれば、2~3日出ない赤ちゃんもいます。便秘になると、赤ちゃんがぐずったり不機嫌になるのですぐに解ります。
お風呂上がりにおなかを時計回りにマッサージしてみましょう。マッサージで効果がなければ、綿棒浣腸という方法もあります。綿棒にベビーオイルやグリセリンを浸し、赤ちゃんの肛門を刺激します。ただし、自分で排便できるようにするために、綿棒浣腸はあまり行わないようにします。
■睡眠
夜中に1回や2回赤ちゃんが泣くことは避けられないものです。しかし、一晩に3.4回以上泣いたり、1~2時間間隔で泣くような夜泣きぐせをおこす赤ちゃんも少なくありません。睡眠を妨げる原因がないかチェックしてください。
部屋と布団の温度、おむつ、衣服(窮屈・しわなど)、ベッド(狭くないか)、姿勢(好きな姿勢があります)、かゆみ、痛みなど。
これらに対応しても夜泣きがおさまらなければ、きっとその子は根っからエネルギーの強い子なのだと思われます。
添い寝をするか、できるだけママのそばに寝かせ、ぐずり始めたらすぐになだめられるようにすると良いでしょう。
■不快状況
生まれたばかりの赤ちゃんが泣きだす場合、考えられる理由は主に、おっぱいの不足、おむつの不快、湿疹などのかゆみ、暑さ・寒さ、衣類の不快(窮屈・しわなど)です。
このような不快がないか調べてあげましょう。
■不安
生後1ヶ月を過ぎると、心も成長し、泣く理由も高度になっていきます。例えば、 なれない環境、人見知り、ママがいない、嫌いな音がする、などの理由で赤ちゃんは不安を感じて泣きます。また、その他の心理的な原因(イライラや遊んでほしいなど)で泣くこともあります。心理的な理由で泣いいてる場合の対処方法は、赤ちゃんによって違うので、いろいろ試してそれぞれの赤ちゃんに合ったあやし方を見つけてください。
■便秘
排便には個人差があり、毎日排便のある赤ちゃんもいれば、2~3日出ない赤ちゃんもいます。便秘になると、赤ちゃんがぐずったり不機嫌になるのですぐに解ります。
お風呂上がりにおなかを時計回りにマッサージしてみましょう。マッサージで効果がなければ、綿棒浣腸という方法もあります。綿棒にベビーオイルやグリセリンを浸し、赤ちゃんの肛門を刺激します。ただし、自分で排便できるようにするために、綿棒浣腸はあまり行わないようにします。
■睡眠
夜中に1回や2回赤ちゃんが泣くことは避けられないものです。しかし、一晩に3.4回以上泣いたり、1~2時間間隔で泣くような夜泣きぐせをおこす赤ちゃんも少なくありません。睡眠を妨げる原因がないかチェックしてください。
部屋と布団の温度、おむつ、衣服(窮屈・しわなど)、ベッド(狭くないか)、姿勢(好きな姿勢があります)、かゆみ、痛みなど。
これらに対応しても夜泣きがおさまらなければ、きっとその子は根っからエネルギーの強い子なのだと思われます。
添い寝をするか、できるだけママのそばに寝かせ、ぐずり始めたらすぐになだめられるようにすると良いでしょう。
Posted by mamabuddy at
03:04
│Comments(0)
2007年03月21日
赤ちゃんに快適な空間とは(温度・清潔・ママの声・抱き方など)
■温度
赤ちゃんの快適温度は18度~24度くらいです。湿度は50から60%が適当です。
夏にクーラーを使用する際は、外気との温度差を4~5度程度にして、室温は25度くらいにすると良いでしょう。冬は、空気が乾燥しているとかぜをひきやすくなるので、加湿器などで調節しましょう。冷やしすぎ、暖めすぎに注意し、換気に充分気を配りましょう。
■清潔
生まれたての赤ちゃんは新陳代謝が活発で、皮脂分泌が盛んです。また、動いたり泣いたりして、たくさん汗をかきますし、おむつや授乳によって、想像以上に赤ちゃんのからだは汚れがちです。1日に1回は顔や身体を石鹸でよく洗い、皮脂を落としてください。くびれたところは念入りに洗いましょう。
肌着はこまめに取り替えてあげましょう。
■ママの声
赤ちゃんはママの声を聞いたり、ママと見つめ合ったりするのが大好きです。ママの言葉の意味がわからなくても、赤ちゃんはママに話しかけられることで喜び、それが安心感や信頼感へとつながっていきます。おっぱいやおむつ替えの時は、大切なコミュニケーションの機会ですから、赤ちゃんの顔を見てやさしく声をかけてあげましょう。2~3ヶ月頃になると、機嫌のいい時は「アー」「ウー」とうれしい気持ちを表現してくれるようになります。
■抱き方
生まれたての赤ちゃんを、はれものにさわるように扱う必要はありません。むしろ寝かせたままよりも、抱いて動かしてあげた方がいい運動になりますし、精神面でもママとのつながりが強まり、赤ちゃんが安心して落ち着きます。
まずは、授乳の前後やおむつ替えの時に、しばらく抱いてあげましょう。授乳の前には、顔を向き合わせてあやしながら、軽く上下に動かすと目を覚ましたり、落ち着いたりします。授乳後は、肩に立てかけるように縦抱きするとゲップが出やすいでしょう。ぐずるのを静まらせたり、あやすために抱く時は、赤ちゃんの頭を二の腕にもたれさせ、頭を少し高めにして斜め抱きにすると良いでしょう。水平に抱くと、たいていの赤ちゃんが落ち着かないようです。縦抱きが落ち着く子もいます。
赤ちゃんの快適温度は18度~24度くらいです。湿度は50から60%が適当です。
夏にクーラーを使用する際は、外気との温度差を4~5度程度にして、室温は25度くらいにすると良いでしょう。冬は、空気が乾燥しているとかぜをひきやすくなるので、加湿器などで調節しましょう。冷やしすぎ、暖めすぎに注意し、換気に充分気を配りましょう。
■清潔
生まれたての赤ちゃんは新陳代謝が活発で、皮脂分泌が盛んです。また、動いたり泣いたりして、たくさん汗をかきますし、おむつや授乳によって、想像以上に赤ちゃんのからだは汚れがちです。1日に1回は顔や身体を石鹸でよく洗い、皮脂を落としてください。くびれたところは念入りに洗いましょう。
肌着はこまめに取り替えてあげましょう。
■ママの声
赤ちゃんはママの声を聞いたり、ママと見つめ合ったりするのが大好きです。ママの言葉の意味がわからなくても、赤ちゃんはママに話しかけられることで喜び、それが安心感や信頼感へとつながっていきます。おっぱいやおむつ替えの時は、大切なコミュニケーションの機会ですから、赤ちゃんの顔を見てやさしく声をかけてあげましょう。2~3ヶ月頃になると、機嫌のいい時は「アー」「ウー」とうれしい気持ちを表現してくれるようになります。
■抱き方
生まれたての赤ちゃんを、はれものにさわるように扱う必要はありません。むしろ寝かせたままよりも、抱いて動かしてあげた方がいい運動になりますし、精神面でもママとのつながりが強まり、赤ちゃんが安心して落ち着きます。
まずは、授乳の前後やおむつ替えの時に、しばらく抱いてあげましょう。授乳の前には、顔を向き合わせてあやしながら、軽く上下に動かすと目を覚ましたり、落ち着いたりします。授乳後は、肩に立てかけるように縦抱きするとゲップが出やすいでしょう。ぐずるのを静まらせたり、あやすために抱く時は、赤ちゃんの頭を二の腕にもたれさせ、頭を少し高めにして斜め抱きにすると良いでしょう。水平に抱くと、たいていの赤ちゃんが落ち着かないようです。縦抱きが落ち着く子もいます。
Posted by mamabuddy at
02:59
│Comments(0)
2007年03月21日
赤ちゃんに快適な空間とは(温度・清潔・ママの声・抱き方など)
■温度
赤ちゃんの快適温度は18度~24度くらいです。湿度は50から60%が適当です。
夏にクーラーを使用する際は、外気との温度差を4~5度程度にして、室温は25度くらいにすると良いでしょう。冬は、空気が乾燥しているとかぜをひきやすくなるので、加湿器などで調節しましょう。冷やしすぎ、暖めすぎに注意し、換気に充分気を配りましょう。
■清潔
生まれたての赤ちゃんは新陳代謝が活発で、皮脂分泌が盛んです。また、動いたり泣いたりして、たくさん汗をかきますし、おむつや授乳によって、想像以上に赤ちゃんのからだは汚れがちです。1日に1回は顔や身体を石鹸でよく洗い、皮脂を落としてください。くびれたところは念入りに洗いましょう。
肌着はこまめに取り替えてあげましょう。
■ママの声
赤ちゃんはママの声を聞いたり、ママと見つめ合ったりするのが大好きです。ママの言葉の意味がわからなくても、赤ちゃんはママに話しかけられることで喜び、それが安心感や信頼感へとつながっていきます。おっぱいやおむつ替えの時は、大切なコミュニケーションの機会ですから、赤ちゃんの顔を見てやさしく声をかけてあげましょう。2~3ヶ月頃になると、機嫌のいい時は「アー」「ウー」とうれしい気持ちを表現してくれるようになります。
■抱き方
生まれたての赤ちゃんを、はれものにさわるように扱う必要はありません。むしろ寝かせたままよりも、抱いて動かしてあげた方がいい運動になりますし、精神面でもママとのつながりが強まり、赤ちゃんが安心して落ち着きます。
まずは、授乳の前後やおむつ替えの時に、しばらく抱いてあげましょう。授乳の前には、顔を向き合わせてあやしながら、軽く上下に動かすと目を覚ましたり、落ち着いたりします。授乳後は、肩に立てかけるように縦抱きするとゲップが出やすいでしょう。ぐずるのを静まらせたり、あやすために抱く時は、赤ちゃんの頭を二の腕にもたれさせ、頭を少し高めにして斜め抱きにすると良いでしょう。水平に抱くと、たいていの赤ちゃんが落ち着かないようです。縦抱きが落ち着く子もいます。
赤ちゃんの快適温度は18度~24度くらいです。湿度は50から60%が適当です。
夏にクーラーを使用する際は、外気との温度差を4~5度程度にして、室温は25度くらいにすると良いでしょう。冬は、空気が乾燥しているとかぜをひきやすくなるので、加湿器などで調節しましょう。冷やしすぎ、暖めすぎに注意し、換気に充分気を配りましょう。
■清潔
生まれたての赤ちゃんは新陳代謝が活発で、皮脂分泌が盛んです。また、動いたり泣いたりして、たくさん汗をかきますし、おむつや授乳によって、想像以上に赤ちゃんのからだは汚れがちです。1日に1回は顔や身体を石鹸でよく洗い、皮脂を落としてください。くびれたところは念入りに洗いましょう。
肌着はこまめに取り替えてあげましょう。
■ママの声
赤ちゃんはママの声を聞いたり、ママと見つめ合ったりするのが大好きです。ママの言葉の意味がわからなくても、赤ちゃんはママに話しかけられることで喜び、それが安心感や信頼感へとつながっていきます。おっぱいやおむつ替えの時は、大切なコミュニケーションの機会ですから、赤ちゃんの顔を見てやさしく声をかけてあげましょう。2~3ヶ月頃になると、機嫌のいい時は「アー」「ウー」とうれしい気持ちを表現してくれるようになります。
■抱き方
生まれたての赤ちゃんを、はれものにさわるように扱う必要はありません。むしろ寝かせたままよりも、抱いて動かしてあげた方がいい運動になりますし、精神面でもママとのつながりが強まり、赤ちゃんが安心して落ち着きます。
まずは、授乳の前後やおむつ替えの時に、しばらく抱いてあげましょう。授乳の前には、顔を向き合わせてあやしながら、軽く上下に動かすと目を覚ましたり、落ち着いたりします。授乳後は、肩に立てかけるように縦抱きするとゲップが出やすいでしょう。ぐずるのを静まらせたり、あやすために抱く時は、赤ちゃんの頭を二の腕にもたれさせ、頭を少し高めにして斜め抱きにすると良いでしょう。水平に抱くと、たいていの赤ちゃんが落ち着かないようです。縦抱きが落ち着く子もいます。
Posted by mamabuddy at
02:59
│Comments(0)