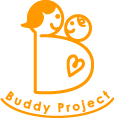2006年10月25日
第5回 マザーカウンセリング2
<第五回研修会>
会 期:2006年9月20日(水) 10:00~11:30
会 場:アイセル21
講 師:柴田 俊一先生(臨床心理士、浜松市子育て家庭支援センター 所長)
テーマ:マザーカウンセリング
演 題:サポートに必要な話を聞く技術とこころ
以下、講演修了後に報告資料を掲載します。
会 期:2006年9月20日(水) 10:00~11:30
会 場:アイセル21
講 師:柴田 俊一先生(臨床心理士、浜松市子育て家庭支援センター 所長)
テーマ:マザーカウンセリング
演 題:サポートに必要な話を聞く技術とこころ
以下、講演修了後に報告資料を掲載します。
講演会エビデンス、現在、作成中ですが、講座の受講生(ママバディ)が
お話の内容をまとめましたので、以下に明記しておきます。
===========================================
・エンパワーメント(パワーをつける。力づけられること)
子育て支援分野などでは、その人にエンパワーメントできるかがテーマ
1.親の育児不安を軽減するには
育児不安の背景
・病気…子供にある場合
・発達の遅れ…検診時他の子と比べて、「うちの子はできない」と不安
・こころの問題…子供のノイローゼ
・家庭関係…このギクシャク感が子供に影響を与える。(子供は家庭の中で弱い存在の為)
不登校などの具合の悪い子の背景には、家庭関係のギクシャク有り
2.どうしたら育児不安は軽減できるのか
・知識を得る→知識を与える
・スキルを(技術)を身に付ける→スキルを教える
例)おしっこに連れて行くタイミング
だだをこねている子のなだめ方
子供同士のケンカの仲裁 → 親は自分の親にやってもらったとおりにやる
→しかし子供によって対応が違うし、他の家族も関わってきてしまう
→今までのスキル通りにはいかない
・気持ちを切り替える→気持ちを聞き取る(カウンセリング的な対応)
3.話をするということ
聞くだけの仕事ではカウンセリングの部分がない。
グループで話し合ったり電話相談などがあるが、カウンセラーは丁寧に話を聞くことが重要。
4.話をすることの意味
・カタルシス(話をすることによって気がすんだ)を得る
カタルシスとは気がすむ、住む、済む、澄むということで、鎮静化していく状態
・自分のことを分かってもらう(話す・放つ)=心の中を解き放つ、つまりカタルシス
言語化することによって、つらい気持ちの気が晴れる
言語に載せて、自分の気持ちを伝える
しゃべりながら、自分のことを再確認する
・聞き役がいることによって、自分のことがはっきりしてくる(丁寧な聞き役が必要)
言葉のキャッチボールができるテープレコーダに向かってしゃべることとは違う
(生身の人間が聞いてくれたと確認しないと聞いてもらった気がしない)
メールでは音声に言語を載せない為、カウンセリングではなくなる
5.話をしたくなる条件
目の前の人が、攻撃や批判をせずあるがままを受け止めてくれるとき
・安全であると感じられるとき
・自分の価値観と生活経験が認められ、尊重されたとき
・聞いてくれる相手がいるとき
・お互いに支えあっているグループに入っていると実感できるとき(皆にサポートされている)
6.話を聞く2つのポイント
1)お互いの価値観を尊重する
・聞き取りはその人の価値観を変えることを目的としない
・相手の価値観(相手が大事にしているもの)を尊重する、つまり違うと否定してはいけない。
相手の考えには理由がある。
2)経験(体験)学習サイクルを尊重する
・指導はしない。問いかけをして、相手に自分の忘れていたことや、片隅の情報にきづいてもらう
・同じものでも価値観はちがう
例)一円玉の大きさを書いてください(外国での調査による)
大きく書く→低所得者、小さく書く→高所得者
7.体験学習サイクル
出来事・体験。次にどう活かすか、応用、認識、事実の確認
これからどうするのか?何が起きたのか?関連付け・意味を考える・それはどういうことか
・出来事(Experience)
例)公園に散歩に行こうと思って歩いていたら、何か聞こえたので振り向いたら転んでしまった。
・事実の確認(Noticing)
いろいろな点を押さえて確かめる
いつ? 「昼食後、久しぶりに公園に行った」
だれが? 「友人が来ていて、ベンチで話をした」
何を?なぜ? 「誰かの声がするので振り向き転んだ」
どのように?「そういえば、昼食時から何か聞こえた気が」 どうなった?
そのときの子供のご機嫌は?
・意味を考える(Relating)
つながりをつける。
「あれ」がどんな意味を持っているのか問い掛ける
「どうかんじたのか」、「何を思い起こすのか」、「そのような状況から気づいたことは?」
「(そのような経験はあなたにとって)どのような意味があるのだろうか?」
・質問には2種類ある。
開かれた質問と閉じられた質問である。
開かれた質問はさまざまな回答があるが、閉じられた質問は、答えが一つしか出てこない。
閉かれた質問
例)熱は何度でしたか?、○○は好きですか?、そのときそこにいたのですね
開かれた質問
例)そのときどんな感じでしたか?、それから、どうしたんですか?もう少し詳しく教えて下さい
私は経験したことがないのですが…
・相槌にもさまざまな形態がある
例)はい、うん、へー!、そう(そうなんだ)、なるほど、それで、わかりますよ
それで、どうなったのですか
・次にどう生かすか(Apply)
これからの話し合いにどう活かすかに焦点をあてる
「今ならどういうふうに聴きますか」、「どんな新しい選択肢を考えましたか?」
・体験サイクルの例
①車で走っている
違う道から行こう、渋滞している、救急車が走っている、事故が起きたんだ
②(子)消しゴムがない
今回体験したことによって (子)「消しゴムがなくなっちゃった」
自分で探すことがわかる
(親)TVの裏に落ちているがすぐに言わない
(親)一緒に考えよう「最初はどこで使ったの?」、「どんな色の消しゴムだった?」
いろいろ質問してみる
(子)いろいろ思い出してくる→探す→「TVの裏にあった」
③子供が泣いている
どうして?わからない。私はだめな母親だ・・。イライラ…
③において、サポーターとして対処する場合指示するような対処法ではいけない。
母親達が自分たち自身、物事をで決められなくなってしまう。
そして、他人を頼るようになりその人自身が育っていかなくなる。
サポーターが母親達に要求されたことを次々にやってしまうことは、
パワーメント(パワーをつける・力づけられる事)とは逆になるのである。
よって、子育て広場などにおいても、やりすぎるのではなく、
母親達に考えをもらうほうがよい。
やりすぎてしまうことは、逆にあなたは、何もできない人と言っているようなものなのだ。
8.聴く実習のポイント
・心理的な現象
この絵をすう秒間見て覚えてください。
そして、この絵を隠して覚えているか書いてみてください。
結果、同じ絵を見ても一人一人受け止め方、同じ絵を見てもイメージは違う。
9.積極的傾聴
・「聴く」ことは受動的なことではない。「聴いていますよ」という積極的な意思が必要
・聴く側のある程度の自己開示も必要。
「私もそうだったわよ」と言えば、「この人も子育てしたことがあるんだ」と共感できる。
しかし、肯定的意見ばかりではなく「今の話不愉快よ」と否定的意見を言う必要な事もある。
そうすることによって相手も、「自分の思っていることを言ってもいいんだ」と考えるようになる。
・情動調律「チューニング」
赤ちゃんが「泣く」。すると母親は「どうしたの?」と高い声で話し掛ける。
→赤ちゃんの情動も合わせる。(相手に合わせるということ)
・「オープナー特性」自己開示、共感
10.実習
お話の内容をまとめましたので、以下に明記しておきます。
===========================================
・エンパワーメント(パワーをつける。力づけられること)
子育て支援分野などでは、その人にエンパワーメントできるかがテーマ
1.親の育児不安を軽減するには
育児不安の背景
・病気…子供にある場合
・発達の遅れ…検診時他の子と比べて、「うちの子はできない」と不安
・こころの問題…子供のノイローゼ
・家庭関係…このギクシャク感が子供に影響を与える。(子供は家庭の中で弱い存在の為)
不登校などの具合の悪い子の背景には、家庭関係のギクシャク有り
2.どうしたら育児不安は軽減できるのか
・知識を得る→知識を与える
・スキルを(技術)を身に付ける→スキルを教える
例)おしっこに連れて行くタイミング
だだをこねている子のなだめ方
子供同士のケンカの仲裁 → 親は自分の親にやってもらったとおりにやる
→しかし子供によって対応が違うし、他の家族も関わってきてしまう
→今までのスキル通りにはいかない
・気持ちを切り替える→気持ちを聞き取る(カウンセリング的な対応)
3.話をするということ
聞くだけの仕事ではカウンセリングの部分がない。
グループで話し合ったり電話相談などがあるが、カウンセラーは丁寧に話を聞くことが重要。
4.話をすることの意味
・カタルシス(話をすることによって気がすんだ)を得る
カタルシスとは気がすむ、住む、済む、澄むということで、鎮静化していく状態
・自分のことを分かってもらう(話す・放つ)=心の中を解き放つ、つまりカタルシス
言語化することによって、つらい気持ちの気が晴れる
言語に載せて、自分の気持ちを伝える
しゃべりながら、自分のことを再確認する
・聞き役がいることによって、自分のことがはっきりしてくる(丁寧な聞き役が必要)
言葉のキャッチボールができるテープレコーダに向かってしゃべることとは違う
(生身の人間が聞いてくれたと確認しないと聞いてもらった気がしない)
メールでは音声に言語を載せない為、カウンセリングではなくなる
5.話をしたくなる条件
目の前の人が、攻撃や批判をせずあるがままを受け止めてくれるとき
・安全であると感じられるとき
・自分の価値観と生活経験が認められ、尊重されたとき
・聞いてくれる相手がいるとき
・お互いに支えあっているグループに入っていると実感できるとき(皆にサポートされている)
6.話を聞く2つのポイント
1)お互いの価値観を尊重する
・聞き取りはその人の価値観を変えることを目的としない
・相手の価値観(相手が大事にしているもの)を尊重する、つまり違うと否定してはいけない。
相手の考えには理由がある。
2)経験(体験)学習サイクルを尊重する
・指導はしない。問いかけをして、相手に自分の忘れていたことや、片隅の情報にきづいてもらう
・同じものでも価値観はちがう
例)一円玉の大きさを書いてください(外国での調査による)
大きく書く→低所得者、小さく書く→高所得者
7.体験学習サイクル
出来事・体験。次にどう活かすか、応用、認識、事実の確認
これからどうするのか?何が起きたのか?関連付け・意味を考える・それはどういうことか
・出来事(Experience)
例)公園に散歩に行こうと思って歩いていたら、何か聞こえたので振り向いたら転んでしまった。
・事実の確認(Noticing)
いろいろな点を押さえて確かめる
いつ? 「昼食後、久しぶりに公園に行った」
だれが? 「友人が来ていて、ベンチで話をした」
何を?なぜ? 「誰かの声がするので振り向き転んだ」
どのように?「そういえば、昼食時から何か聞こえた気が」 どうなった?
そのときの子供のご機嫌は?
・意味を考える(Relating)
つながりをつける。
「あれ」がどんな意味を持っているのか問い掛ける
「どうかんじたのか」、「何を思い起こすのか」、「そのような状況から気づいたことは?」
「(そのような経験はあなたにとって)どのような意味があるのだろうか?」
・質問には2種類ある。
開かれた質問と閉じられた質問である。
開かれた質問はさまざまな回答があるが、閉じられた質問は、答えが一つしか出てこない。
閉かれた質問
例)熱は何度でしたか?、○○は好きですか?、そのときそこにいたのですね
開かれた質問
例)そのときどんな感じでしたか?、それから、どうしたんですか?もう少し詳しく教えて下さい
私は経験したことがないのですが…
・相槌にもさまざまな形態がある
例)はい、うん、へー!、そう(そうなんだ)、なるほど、それで、わかりますよ
それで、どうなったのですか
・次にどう生かすか(Apply)
これからの話し合いにどう活かすかに焦点をあてる
「今ならどういうふうに聴きますか」、「どんな新しい選択肢を考えましたか?」
・体験サイクルの例
①車で走っている
違う道から行こう、渋滞している、救急車が走っている、事故が起きたんだ
②(子)消しゴムがない
今回体験したことによって (子)「消しゴムがなくなっちゃった」
自分で探すことがわかる
(親)TVの裏に落ちているがすぐに言わない
(親)一緒に考えよう「最初はどこで使ったの?」、「どんな色の消しゴムだった?」
いろいろ質問してみる
(子)いろいろ思い出してくる→探す→「TVの裏にあった」
③子供が泣いている
どうして?わからない。私はだめな母親だ・・。イライラ…
③において、サポーターとして対処する場合指示するような対処法ではいけない。
母親達が自分たち自身、物事をで決められなくなってしまう。
そして、他人を頼るようになりその人自身が育っていかなくなる。
サポーターが母親達に要求されたことを次々にやってしまうことは、
パワーメント(パワーをつける・力づけられる事)とは逆になるのである。
よって、子育て広場などにおいても、やりすぎるのではなく、
母親達に考えをもらうほうがよい。
やりすぎてしまうことは、逆にあなたは、何もできない人と言っているようなものなのだ。
8.聴く実習のポイント
・心理的な現象
この絵をすう秒間見て覚えてください。
そして、この絵を隠して覚えているか書いてみてください。
結果、同じ絵を見ても一人一人受け止め方、同じ絵を見てもイメージは違う。
9.積極的傾聴
・「聴く」ことは受動的なことではない。「聴いていますよ」という積極的な意思が必要
・聴く側のある程度の自己開示も必要。
「私もそうだったわよ」と言えば、「この人も子育てしたことがあるんだ」と共感できる。
しかし、肯定的意見ばかりではなく「今の話不愉快よ」と否定的意見を言う必要な事もある。
そうすることによって相手も、「自分の思っていることを言ってもいいんだ」と考えるようになる。
・情動調律「チューニング」
赤ちゃんが「泣く」。すると母親は「どうしたの?」と高い声で話し掛ける。
→赤ちゃんの情動も合わせる。(相手に合わせるということ)
・「オープナー特性」自己開示、共感
10.実習
【講演会】3/4(土)「見えない!子どもの貧困のリアル」
【講演会】出産・子育てをキャリアにするという生き方
満員御礼!ありがとうございました!!
【講演会】出産・子育てから広がる「わたし」の生き方
6/2(月) 講演会「出産・子育てをキャリアにするという生き方」
静岡新聞で紹介されました!「袰岩奈々さん講演会」
【講演会】出産・子育てをキャリアにするという生き方
満員御礼!ありがとうございました!!
【講演会】出産・子育てから広がる「わたし」の生き方
6/2(月) 講演会「出産・子育てをキャリアにするという生き方」
静岡新聞で紹介されました!「袰岩奈々さん講演会」
Posted by mamabuddy at 12:12│Comments(0)
│子育て講演会