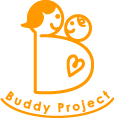2007年07月29日
第7回 子育て相談窓口から
第7回<子育て相談窓口から><第七回研修会>
会 期:2006年11月16日(木) 10:00~11:30
会 場:アイセル21
講 師:長島 茂代さん(静岡市職員 葵区福祉事務所)
池田 文香さん(静岡市職員 保健福祉センター)
テーマ:子育てと行政
演 題:子育て相談窓口から
~サポーターに期待すること、実際の窓口現場~
以下、講演修了後に報告資料を掲載します。
会 期:2006年11月16日(木) 10:00~11:30
会 場:アイセル21
講 師:長島 茂代さん(静岡市職員 葵区福祉事務所)
池田 文香さん(静岡市職員 保健福祉センター)
テーマ:子育てと行政
演 題:子育て相談窓口から
~サポーターに期待すること、実際の窓口現場~
以下、講演修了後に報告資料を掲載します。
講演会エビデンス、現在、作成中ですが、講座の受講生(ママバディ)が
お話の内容をまとめましたので、以下に明記しておきます。
===========================================
(長嶋さんのお話)
家庭児童相談室(保育児童課内)・・・児童相談所の下請け的存在、様々な相談
・役割の流れ
保険福祉センターから相談→一緒に家庭訪問→保育園と連携→児童相談所と相談、保護など
学校では不登校の子供への対応なども行う
・相談を受ける側(子育てサポーター)として気をつけること
・自分のフィールドを考えて活動する
・一般の人と接する機会が多いので困っている人がいたら相談員との架け橋となる。
・相談にのる時に自分の価値観が邪魔をする時があるので注意する。
・自分の正しいという思いを変えていく事も必要なときがある。
・一番の支援は聴くこと。相手の心を聴く。
・言葉かけには多くの配慮が必要。「よく話してくれたね」という思いを持って聴く。
・相談員の方が「ダメだな」と思われてはいけないので自己研鑽が必要。
・心が温かくなると人は元気になるので、そのことを心がけて接する。
・うまくいかない時があったら他の人に相談する。抱え込まない。
(池田さんのお話)
・保健福祉センターと保健所との違い
(保健所)
静岡市保健所と清水支所の2ヶ所ある。感染症や食中毒、シックハウス症候群など
市民の健康をおびやかすものに対処し、市民生活を健康面から守るため、
地域保健衛生行政の拠点として仕事をしている。
(保険福祉センター)
静岡市健康づくり推進課の市民の相談窓口の一つ。
葵区内に4箇所、駿河区内に3箇所、清水区内2箇所の計静岡に9ヶ所設置されている。
子供からお年寄りまで健康づくりのための相談事業を行い、保健、福祉、医療に係る
総合相談を行っている。必要に応じて他の機関と連携を図った支援も行っている。
・活動内容
・母子手帳の発行《最近の傾向》
・妊産婦、新生児に対する訪問指導
→未入籍が多い
・妊産婦健診、乳幼児健診
→出産前後の里帰りが長い→地域からの孤立化
→出産後の手のかかる時期に父親の育児支援が見込めない→父親の育児不参加へ ・一般的な栄養指導
・予防接種
・老人保健サービス 等
・産後のうつ(マタニティーブルー)への対応
抑うつ、興味減退、多睡眠、食欲減になりやすい。ホルモンの変化によるものも有り。
新生児訪問は早期支援を兼ねている。6ヶ月健診ではアンケートをとり、母親の様子を見て
訪問回数を増やしている。
・今の子育てについて
・「子育て支援」「少子化対策」
「支援、対策」ことば自体が女性に対するプレッシャーとなっている。
・子育ては、人の基本的な営みであり、体の本能であるが崩れてきている。→虐待など
・100%成功する子育ての秘訣、正解、高得点、完璧はないのに、母親に求めやすい。
・同じように育てても子供によって違うこと、子供の側に寄り添って育てることに気づきにくい。
・育児書は反論ができにくい。また、正しい情報が自分の子供に合うかはわからない。
・子育てサポーターに望むこと
・お母さんの言い分をよく聴く。
・母親の育てる力(本能)と子供の育つ力を引き出す支援
・「そうだね」という共感だけで充分なこともある。
・高学歴な母親は、勉強すれば高い成果が得られるように、子育ても頑張り、
つまづきを許さない傾向があるので、聴くことによって肩の力を抜く手助けをする。
→「頑張れない時もあって当然」「うまくいかなくて当然」
・自分の体験を出していけないことはないが、自分の判断で決めつけるのは良くない。
→お母さんに選択の余地を残す。
・否定する言葉、マイナスな言葉は言わない。
例)指しゃぶりは愛情不足などの批評は避ける。
・人によっては感じ方が違うので、誉める時は注意が必要。
例)洋服がかわいい(子供本人は?)、目が大きいね。(私に似ていない)
・相手の感情に入り込み過ぎないこと。
・できない時は1人で抱え込まないで行政に相談する。
・子育てサポーターは専門職ではないので、母親に寄り添った活動をしてほしい。
お話の内容をまとめましたので、以下に明記しておきます。
===========================================
(長嶋さんのお話)
家庭児童相談室(保育児童課内)・・・児童相談所の下請け的存在、様々な相談
・役割の流れ
保険福祉センターから相談→一緒に家庭訪問→保育園と連携→児童相談所と相談、保護など
学校では不登校の子供への対応なども行う
・相談を受ける側(子育てサポーター)として気をつけること
・自分のフィールドを考えて活動する
・一般の人と接する機会が多いので困っている人がいたら相談員との架け橋となる。
・相談にのる時に自分の価値観が邪魔をする時があるので注意する。
・自分の正しいという思いを変えていく事も必要なときがある。
・一番の支援は聴くこと。相手の心を聴く。
・言葉かけには多くの配慮が必要。「よく話してくれたね」という思いを持って聴く。
・相談員の方が「ダメだな」と思われてはいけないので自己研鑽が必要。
・心が温かくなると人は元気になるので、そのことを心がけて接する。
・うまくいかない時があったら他の人に相談する。抱え込まない。
(池田さんのお話)
・保健福祉センターと保健所との違い
(保健所)
静岡市保健所と清水支所の2ヶ所ある。感染症や食中毒、シックハウス症候群など
市民の健康をおびやかすものに対処し、市民生活を健康面から守るため、
地域保健衛生行政の拠点として仕事をしている。
(保険福祉センター)
静岡市健康づくり推進課の市民の相談窓口の一つ。
葵区内に4箇所、駿河区内に3箇所、清水区内2箇所の計静岡に9ヶ所設置されている。
子供からお年寄りまで健康づくりのための相談事業を行い、保健、福祉、医療に係る
総合相談を行っている。必要に応じて他の機関と連携を図った支援も行っている。
・活動内容
・母子手帳の発行《最近の傾向》
・妊産婦、新生児に対する訪問指導
→未入籍が多い
・妊産婦健診、乳幼児健診
→出産前後の里帰りが長い→地域からの孤立化
→出産後の手のかかる時期に父親の育児支援が見込めない→父親の育児不参加へ ・一般的な栄養指導
・予防接種
・老人保健サービス 等
・産後のうつ(マタニティーブルー)への対応
抑うつ、興味減退、多睡眠、食欲減になりやすい。ホルモンの変化によるものも有り。
新生児訪問は早期支援を兼ねている。6ヶ月健診ではアンケートをとり、母親の様子を見て
訪問回数を増やしている。
・今の子育てについて
・「子育て支援」「少子化対策」
「支援、対策」ことば自体が女性に対するプレッシャーとなっている。
・子育ては、人の基本的な営みであり、体の本能であるが崩れてきている。→虐待など
・100%成功する子育ての秘訣、正解、高得点、完璧はないのに、母親に求めやすい。
・同じように育てても子供によって違うこと、子供の側に寄り添って育てることに気づきにくい。
・育児書は反論ができにくい。また、正しい情報が自分の子供に合うかはわからない。
・子育てサポーターに望むこと
・お母さんの言い分をよく聴く。
・母親の育てる力(本能)と子供の育つ力を引き出す支援
・「そうだね」という共感だけで充分なこともある。
・高学歴な母親は、勉強すれば高い成果が得られるように、子育ても頑張り、
つまづきを許さない傾向があるので、聴くことによって肩の力を抜く手助けをする。
→「頑張れない時もあって当然」「うまくいかなくて当然」
・自分の体験を出していけないことはないが、自分の判断で決めつけるのは良くない。
→お母さんに選択の余地を残す。
・否定する言葉、マイナスな言葉は言わない。
例)指しゃぶりは愛情不足などの批評は避ける。
・人によっては感じ方が違うので、誉める時は注意が必要。
例)洋服がかわいい(子供本人は?)、目が大きいね。(私に似ていない)
・相手の感情に入り込み過ぎないこと。
・できない時は1人で抱え込まないで行政に相談する。
・子育てサポーターは専門職ではないので、母親に寄り添った活動をしてほしい。
【講演会】3/4(土)「見えない!子どもの貧困のリアル」
【講演会】出産・子育てをキャリアにするという生き方
満員御礼!ありがとうございました!!
【講演会】出産・子育てから広がる「わたし」の生き方
6/2(月) 講演会「出産・子育てをキャリアにするという生き方」
静岡新聞で紹介されました!「袰岩奈々さん講演会」
【講演会】出産・子育てをキャリアにするという生き方
満員御礼!ありがとうございました!!
【講演会】出産・子育てから広がる「わたし」の生き方
6/2(月) 講演会「出産・子育てをキャリアにするという生き方」
静岡新聞で紹介されました!「袰岩奈々さん講演会」
Posted by mamabuddy at 07:29│Comments(0)
│子育て講演会