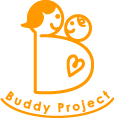2008年01月01日
第8回 親と親をつなぐ
<第八回研修会>
会 期:2006年12月21日(水) 10:00~11:30
会 場:アイセル21
講 師:岡村 由紀子先生(臨床発達心理士、保育士、あおぞらキンダーガーデン 園長)
テーマ:保育・食育
演 題:親と親をつなぐ
~こどもと大人の心を知る~
以下、講演修了後に報告資料を掲載します。
会 期:2006年12月21日(水) 10:00~11:30
会 場:アイセル21
講 師:岡村 由紀子先生(臨床発達心理士、保育士、あおぞらキンダーガーデン 園長)
テーマ:保育・食育
演 題:親と親をつなぐ
~こどもと大人の心を知る~
以下、講演修了後に報告資料を掲載します。
講演会エビデンス、現在、作成中ですが、講座の受講生(ママバディ)が
お話の内容をまとめましたので、以下に明記しておきます。
===========================================
<導入>
・講師の説明で、指定された状況の絵を描く
⇒ 受講生みな、思い思いの絵を描く。講師が言葉で説明したことが、一人ひとり受け止め方が異なり、とらえ方は様々である。このように大人でも言葉で伝えることは難しいのに、子どもにはもっと伝わりにくい。言葉に頼りすぎて、心と心をつなぐコミュニケーションを忘れている。
★はじめに
*教育・子育ては、私たち自身の中に【人間らしく生きていく力】を育てること
=自己肯定感を育てていくこと
現代は、何かあるとすぐ占い、宗教などに走る・・・→ 自己肯定感がもちにくい
*子どもが人間として大きくなる時
自我・・・DNAと自己肯定感
自分をしっかり受け止めてくれる大人がいれば、子は育つ。
①子どもと大人 ⇒ ②大人と子ども達 ⇒ ③子どものみ
Ⅰ)こどもの心を知る
1.乳幼児期の特徴
・人間としての感性的土台を育てる時期
文字や言葉より、経験や活動を通して覚えていく(例:お手玉、あやとり)
大人の感性は、幼児期に作られるもの・・・「三つ子の魂百まで」
自己決定する、人との違いを認める能力を育てる時期である
2.発達とは何か?
・縦の発達と横の発達
縦の発達・・・身体の成長、歩けるようになる ⇒ 「見える」部分
・横の発達・・・でこぼこ道などを歩く力、スキップ ⇒ 「見えない」部分
歩く力を横に広げる豊かさ ← ここに心を寄せることが大切
・生理的発達と情動(人と人が心を通い合わせる)発達
↓ 赤ちゃんの自我は、たくさんの人のはたらきかけによって育つ
声かけ → ○自我 ← 声かけ
↑
(例)泣く →「どうしたの?」 → 抱っこする → 泣き止む
おむつ交換時には必ず声をかけている
赤ちゃんの笑い声を聞けば、嬉しい!
赤ちゃんの要求(泣くなど)に対し、大人がそのサインをひろう
⇒ 感情が育つ(人見知り→他者理解) 共有する感覚(指差し、ワンワン→ワンワンだね)
3.乳幼児の発達(自我形成の視点から)
0歳児:基本的信頼感
周りの大人がはたらきかけることによって、赤ちゃんの自我が膨らむ
大人の教育力を子どもが引き出してくれている
1歳児:自我の芽生え
指差しが始まる
お母さんへの眼差しをひろうことが大切
2歳児:自我の芽生えを豊かに
比較がわかるようになる 他者が見えてくる(自分がわかる)
だだこねと立ち直り
Ⅰ,2歳児の言葉への頼りすぎは禁物
3歳児:自我の確立
自己主張期 他者が見えている
友達、先生、園 みんな大好き
4歳児:第2の自我の誕生
みんなの中での自分が大切 “わがまま”という自己主張を、
仲間の中でそぎ落としてもらう(共感してもらう)
他律(人からいわれる)と自律(自分から)
自律的コントロールを育てるためには、仲間が必要
嬉しかった経験を内在していく
5歳児:第2の自我を豊かに
合意形成能力期
話し合いで決めていく 話をすると心が澄んでくる
「○○ちゃんは、そう思うのね」 受け止めること(in you)
4.あそびについて
・あそび=面白さの追求活動
・面白くなければ、あそびではない!
・あそびの発達的意義
身体的能力、知的能力、社会性能力をつくる点にあり、
これは自分らしさの感性的土壌を形成するものとなる。
このことが、後の人格の根っこになる重要な点である。
・こどもの遊びの変化
5.幼児期に育てる力
「自己選択・自己決定と他者肯定」
*「受け止める」(in you)と「わがまま」(with you)の違い
◎“受け止める”とは
子どもの要求を徹底的にまるごと受容すること。大人や他者のすすめや指示に動かされるのではなく、その子が自分で選び、決定したことを認めること。結果、その子望むようにならなかったとしても、そのことも含めて受け止めることである。
◎“わがまま”とは
こどもが要求した通りにした後で、結果が思わしくないからと放り出し、さらに大人がそれを容認してしまい、後処理を行ってしまうこと
★自己選択、自己決定した子は、仲間の選択決定も認めてあげることができる
自己選択・自己決定 → 受容 → 自己信頼感 自己肯定感 → 他者には自分と異なる要求があることを知る ⇒ 他者肯定
Ⅱ)大人心を知る
1.こどもの中に見える大人の姿
・こどもの中に社会を見る ⇒ 「見える」ことと「見えない」こと
・「見える」ことを通して、「見えない」気持ちを、その人なりのありのままに受け止めることが大切である
○「in you」 ・・・ その人のその人なりの気持ちを受け止める (共感)
2.現代の子育て状況・・・
親がこども時代を奪われている
★子どもが育つ条件
<昔>
①家族・・・食材を畑や田んぼで作り、家族で収穫したものを料理、消費する、家・家具を作る、修理する、病気になったら看病する、新たな家族が誕生、育児に家族全員が参加、一家団欒など。家族一人一人には多くの仕事があり、結局、子育てはこれらの仕事を担うことができる一人前の子どもを育てることであった。
②子どもは、家事労働の多い母親の相手にしてもらえず、地域に出て異年齢の子ども集団に巻き込まれた。ガキ大将の存在、ケンカして相手の痛みを知る、手加減を覚える、仲間と関わる技法を身につける、責任を負う練習をした。⇒ 「昔は、子育ち環境が豊かにあった」(モノを作る文化と遊びの豊かさ)
★子どもが育つ条件
<今>
①現代の家族
・核家族化、生活現場と労働現場は分かれ、距離が離れる。便利な電化製品、外注化。育児は、外注化できない。家庭にそのまま残る。でも話し相手はいない。家族は自分と子どもだけ、アドバイザーはいない。モデルもいない(塩梅が大事で多様なモデルが必要)。父親不在。卑弥呼の時代以来、こんなに女性が子育てをしている時代はない。女性が苦しい時代 24時間こどもと向き合っていなければならない。人間を育てるということはマニュアルどおりにはいかない。「人間は金太郎飴ではない」、子育ては曖昧なもの、曖昧が素敵なのである。「子育てを支援する」というが、人は自分の経験を通してしか、相手に伝えることはできない。当然、価値観や考え方が違う人はたくさんいる。「○○さんは、そう思うんだね」と、相手を肯定することが大切。決して自分の考えを押し付けたり、否定してはいけない。自分も「これでいいんだ」という自己肯定をすることが大切
②子ども
1970年半ばより、3つの間がない。「空間」・・・ひろば。「時間」・・・塾、お稽古事。「仲間」・・・遊び相手がいない(忙しくて)、集団遊びの激減。「現代は、子育ち環境がなく子育てがしにくい」
3.子育て支援とは?
・一方が他者に何かをすることではなく、本来、親のもつ教育力を、どう本人が気づき、引き出せるか?
・他者と比べず、自分の尺度を押し付けず、出来栄えを問わず、「今」の自分をありのままに受け止める
・まず、自分を肯定してあげること、そして一人で悩まず仲間を作ること
・「気を抜きならがの子育て」、ほっとする人間関係をもつ
・子育てをしながら、子どもからたくさんの幸せをもらっている
・子どものまなざしをしっかり受け止め、一人の子どもの命が輝くよう支援していくこと
~ 親は、こどもに親にしてもらう ~
楽しく子育てをするキーワード・ありのまま・・・自己肯定・子育て仲間・・・つながりを作る、自分の成長・こどものまなざしを知る・・・楽しさ
お話の内容をまとめましたので、以下に明記しておきます。
===========================================
<導入>
・講師の説明で、指定された状況の絵を描く
⇒ 受講生みな、思い思いの絵を描く。講師が言葉で説明したことが、一人ひとり受け止め方が異なり、とらえ方は様々である。このように大人でも言葉で伝えることは難しいのに、子どもにはもっと伝わりにくい。言葉に頼りすぎて、心と心をつなぐコミュニケーションを忘れている。
★はじめに
*教育・子育ては、私たち自身の中に【人間らしく生きていく力】を育てること
=自己肯定感を育てていくこと
現代は、何かあるとすぐ占い、宗教などに走る・・・→ 自己肯定感がもちにくい
*子どもが人間として大きくなる時
自我・・・DNAと自己肯定感
自分をしっかり受け止めてくれる大人がいれば、子は育つ。
①子どもと大人 ⇒ ②大人と子ども達 ⇒ ③子どものみ
Ⅰ)こどもの心を知る
1.乳幼児期の特徴
・人間としての感性的土台を育てる時期
文字や言葉より、経験や活動を通して覚えていく(例:お手玉、あやとり)
大人の感性は、幼児期に作られるもの・・・「三つ子の魂百まで」
自己決定する、人との違いを認める能力を育てる時期である
2.発達とは何か?
・縦の発達と横の発達
縦の発達・・・身体の成長、歩けるようになる ⇒ 「見える」部分
・横の発達・・・でこぼこ道などを歩く力、スキップ ⇒ 「見えない」部分
歩く力を横に広げる豊かさ ← ここに心を寄せることが大切
・生理的発達と情動(人と人が心を通い合わせる)発達
↓ 赤ちゃんの自我は、たくさんの人のはたらきかけによって育つ
声かけ → ○自我 ← 声かけ
↑
(例)泣く →「どうしたの?」 → 抱っこする → 泣き止む
おむつ交換時には必ず声をかけている
赤ちゃんの笑い声を聞けば、嬉しい!
赤ちゃんの要求(泣くなど)に対し、大人がそのサインをひろう
⇒ 感情が育つ(人見知り→他者理解) 共有する感覚(指差し、ワンワン→ワンワンだね)
3.乳幼児の発達(自我形成の視点から)
0歳児:基本的信頼感
周りの大人がはたらきかけることによって、赤ちゃんの自我が膨らむ
大人の教育力を子どもが引き出してくれている
1歳児:自我の芽生え
指差しが始まる
お母さんへの眼差しをひろうことが大切
2歳児:自我の芽生えを豊かに
比較がわかるようになる 他者が見えてくる(自分がわかる)
だだこねと立ち直り
Ⅰ,2歳児の言葉への頼りすぎは禁物
3歳児:自我の確立
自己主張期 他者が見えている
友達、先生、園 みんな大好き
4歳児:第2の自我の誕生
みんなの中での自分が大切 “わがまま”という自己主張を、
仲間の中でそぎ落としてもらう(共感してもらう)
他律(人からいわれる)と自律(自分から)
自律的コントロールを育てるためには、仲間が必要
嬉しかった経験を内在していく
5歳児:第2の自我を豊かに
合意形成能力期
話し合いで決めていく 話をすると心が澄んでくる
「○○ちゃんは、そう思うのね」 受け止めること(in you)
4.あそびについて
・あそび=面白さの追求活動
・面白くなければ、あそびではない!
・あそびの発達的意義
身体的能力、知的能力、社会性能力をつくる点にあり、
これは自分らしさの感性的土壌を形成するものとなる。
このことが、後の人格の根っこになる重要な点である。
・こどもの遊びの変化
5.幼児期に育てる力
「自己選択・自己決定と他者肯定」
*「受け止める」(in you)と「わがまま」(with you)の違い
◎“受け止める”とは
子どもの要求を徹底的にまるごと受容すること。大人や他者のすすめや指示に動かされるのではなく、その子が自分で選び、決定したことを認めること。結果、その子望むようにならなかったとしても、そのことも含めて受け止めることである。
◎“わがまま”とは
こどもが要求した通りにした後で、結果が思わしくないからと放り出し、さらに大人がそれを容認してしまい、後処理を行ってしまうこと
★自己選択、自己決定した子は、仲間の選択決定も認めてあげることができる
自己選択・自己決定 → 受容 → 自己信頼感 自己肯定感 → 他者には自分と異なる要求があることを知る ⇒ 他者肯定
Ⅱ)大人心を知る
1.こどもの中に見える大人の姿
・こどもの中に社会を見る ⇒ 「見える」ことと「見えない」こと
・「見える」ことを通して、「見えない」気持ちを、その人なりのありのままに受け止めることが大切である
○「in you」 ・・・ その人のその人なりの気持ちを受け止める (共感)
2.現代の子育て状況・・・
親がこども時代を奪われている
★子どもが育つ条件
<昔>
①家族・・・食材を畑や田んぼで作り、家族で収穫したものを料理、消費する、家・家具を作る、修理する、病気になったら看病する、新たな家族が誕生、育児に家族全員が参加、一家団欒など。家族一人一人には多くの仕事があり、結局、子育てはこれらの仕事を担うことができる一人前の子どもを育てることであった。
②子どもは、家事労働の多い母親の相手にしてもらえず、地域に出て異年齢の子ども集団に巻き込まれた。ガキ大将の存在、ケンカして相手の痛みを知る、手加減を覚える、仲間と関わる技法を身につける、責任を負う練習をした。⇒ 「昔は、子育ち環境が豊かにあった」(モノを作る文化と遊びの豊かさ)
★子どもが育つ条件
<今>
①現代の家族
・核家族化、生活現場と労働現場は分かれ、距離が離れる。便利な電化製品、外注化。育児は、外注化できない。家庭にそのまま残る。でも話し相手はいない。家族は自分と子どもだけ、アドバイザーはいない。モデルもいない(塩梅が大事で多様なモデルが必要)。父親不在。卑弥呼の時代以来、こんなに女性が子育てをしている時代はない。女性が苦しい時代 24時間こどもと向き合っていなければならない。人間を育てるということはマニュアルどおりにはいかない。「人間は金太郎飴ではない」、子育ては曖昧なもの、曖昧が素敵なのである。「子育てを支援する」というが、人は自分の経験を通してしか、相手に伝えることはできない。当然、価値観や考え方が違う人はたくさんいる。「○○さんは、そう思うんだね」と、相手を肯定することが大切。決して自分の考えを押し付けたり、否定してはいけない。自分も「これでいいんだ」という自己肯定をすることが大切
②子ども
1970年半ばより、3つの間がない。「空間」・・・ひろば。「時間」・・・塾、お稽古事。「仲間」・・・遊び相手がいない(忙しくて)、集団遊びの激減。「現代は、子育ち環境がなく子育てがしにくい」
3.子育て支援とは?
・一方が他者に何かをすることではなく、本来、親のもつ教育力を、どう本人が気づき、引き出せるか?
・他者と比べず、自分の尺度を押し付けず、出来栄えを問わず、「今」の自分をありのままに受け止める
・まず、自分を肯定してあげること、そして一人で悩まず仲間を作ること
・「気を抜きならがの子育て」、ほっとする人間関係をもつ
・子育てをしながら、子どもからたくさんの幸せをもらっている
・子どものまなざしをしっかり受け止め、一人の子どもの命が輝くよう支援していくこと
~ 親は、こどもに親にしてもらう ~
楽しく子育てをするキーワード・ありのまま・・・自己肯定・子育て仲間・・・つながりを作る、自分の成長・こどものまなざしを知る・・・楽しさ
【講演会】3/4(土)「見えない!子どもの貧困のリアル」
【講演会】出産・子育てをキャリアにするという生き方
満員御礼!ありがとうございました!!
【講演会】出産・子育てから広がる「わたし」の生き方
6/2(月) 講演会「出産・子育てをキャリアにするという生き方」
静岡新聞で紹介されました!「袰岩奈々さん講演会」
【講演会】出産・子育てをキャリアにするという生き方
満員御礼!ありがとうございました!!
【講演会】出産・子育てから広がる「わたし」の生き方
6/2(月) 講演会「出産・子育てをキャリアにするという生き方」
静岡新聞で紹介されました!「袰岩奈々さん講演会」
Posted by mamabuddy at 03:45│Comments(0)
│子育て講演会