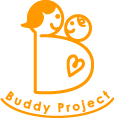2008年01月01日
第9回 産前・産後のメンタル
<第九回研修会>
会 期:2007年1月18日(水) 10:00~11:30
会 場:アイセル21
講 師:新井陽子先生(北里大学病院助産師、同大学大学院修士課程修了)
テーマ:産前・産後のメンタル
演 題:産前・産後のメンタルヘルス
以下、講演修了後に報告資料を掲載します。
会 期:2007年1月18日(水) 10:00~11:30
会 場:アイセル21
講 師:新井陽子先生(北里大学病院助産師、同大学大学院修士課程修了)
テーマ:産前・産後のメンタル
演 題:産前・産後のメンタルヘルス
以下、講演修了後に報告資料を掲載します。
講演会エビデンス、現在、作成中ですが、講座の受講生(ママバディ)が
お話の内容をまとめましたので、以下に明記しておきます。
===========================================
【講義の概要】
女性が妊娠・出産を経て子どもを育てていくという過程には困難・危機的状況になりやすく、主に産後の女性がどのような状況で精神的な危機に陥りやすいのかという視点での講義であった。
【周産期の女性の生活背景】
周産期の女性の心理状態として、母・妻・社会人としての新しい役割の習得という役割遂行に悩んだり、疲れたり、慣れない育児や新しい生活への不安からくる身体的・精神的疲労を感じやすい。出産期の家族の発達課題として新たに子どもが加わることでの家族システムの調整、家事や仕事の役割調達、夫婦や祖父母による子育ての役割調整ということがあげられる。周産期の女性がこの発達課題を乗り越え、うまく適応していくことはとても大変なことである。
【出産した後の感性】
出産した女性は、母親役割のモデルとして一番近い実母の関係性を通し、自分がどのように育てられたかと考える機会を持つ。先生の講義の中に、ある褥婦が、母親から否定的に育てられたということで、自身の出産・子育てにおいて実母との関係に改めて悩んだ方の事例を取り上げていただいた。その事例ではカウンセリングを通し、褥婦が実母との関係を良好に築けることになったという展開であった。
【産後の精神障害】
産後の精神障害については、一過性で特に治療の必要性がないマタニティブルーズから、治療を必要とする産後うつ病の概要について説明があった。マタニティブルーズとは出産直後から一週間ごろまでに出現するもので、涙もろさや抑うつ、疲労、不眠などの症状を主とする。出産した女性の5~7割に認められるものであるが、原因としては心理学的・内分泌学的要因が考えられる。対し産後うつ病とは出産後数週間から数ヶ月以内に出現するもので出産後2週間以内に発症することが多いといわれている。症状や概要はうつ病の診断基準に応じるが、特に産後のうつ病には子どもに対するもの、母親としての自己評価の低下を訴える場合が多い。軽症の場合は看護職による傾聴ですむ場合があるが、重症の場合は精神科医による精神療法や薬物療法が必要となる。
【産後うつ病について】
産後うつ病の発症の心理社会モデルと子どもの発達・発達環境との関連についても説明があった。実質的、情緒的援助の不足や愛着スタイルといったリスクにライフイベントである妊娠・出産が加わると産後うつ病を発症しやすい。また育児サポートの欠如があり、育児への対処機能不全があると産後うつ病を発症するリスクと成り得る。また子どもの発達リスクにも関連し、母子相互作用の障害ともなる。これらのリスクはすべて関連性があることが示されている。
【産後うつ病の検査】
出産した女性が産婦人科を退院する前に、うつ病の危険を点検できる迅速な方法としてEPDS(エジンバラ産後うつ病自己評価スケール)がある。EPDSは10項目の自己記入方式設問からなっており、症状の程度に応じて0から3までのスコアをつけるものである。日本における区分点は8~9点であるが8人に1人は9点以上となるという調査実態がある。EPDSからスクリーニングした女性をピックアップして新生児訪問や面接、電話相談、継続的な家庭訪問といった関わりによりフォロー対象者が減り、最終的な精神科受診が必要なケースはほんのわずかとなったという調査結果についても説明があった。
【産後うつ病の対処】
産後うつ病が疑われたら、あわてず、地域助産師、市町村センターの保健師等に相談をするという窓口の紹介、殆どはカウンセリング・仲間との会話で落ち着く、話すことで気持ちが楽になっていくことについての説明がされた。先生はまとめとして「産後のメンタルヘルスケアにおけるドォーラの役割」を強調された。母親に赤ん坊が生まれると、母親の心は生涯の初期に帰り多くの記憶が蘇ってくる。これらの記憶によって、母親の中に、ケアされたい、守られたいという特別なニーズが呼び起こされてくる。この心理的な退行現象の一部として、母親は安全と感じたい、抱かれてケアを受けたいという気持ちが生まれるというものであった。またこのニーズが満たされていないと母親は、見捨てられ一人ぼっちになったと感じ不安になってくる。これは、母親だけでなく父親も同じニーズを持っている。支援者がいると母親も父親も安全を感じることができ、さらに父親は責任の重さから開放されると、産後のメンタルヘルスケアにおける支援者の役割を示唆していただいた。
お話の内容をまとめましたので、以下に明記しておきます。
===========================================
【講義の概要】
女性が妊娠・出産を経て子どもを育てていくという過程には困難・危機的状況になりやすく、主に産後の女性がどのような状況で精神的な危機に陥りやすいのかという視点での講義であった。
【周産期の女性の生活背景】
周産期の女性の心理状態として、母・妻・社会人としての新しい役割の習得という役割遂行に悩んだり、疲れたり、慣れない育児や新しい生活への不安からくる身体的・精神的疲労を感じやすい。出産期の家族の発達課題として新たに子どもが加わることでの家族システムの調整、家事や仕事の役割調達、夫婦や祖父母による子育ての役割調整ということがあげられる。周産期の女性がこの発達課題を乗り越え、うまく適応していくことはとても大変なことである。
【出産した後の感性】
出産した女性は、母親役割のモデルとして一番近い実母の関係性を通し、自分がどのように育てられたかと考える機会を持つ。先生の講義の中に、ある褥婦が、母親から否定的に育てられたということで、自身の出産・子育てにおいて実母との関係に改めて悩んだ方の事例を取り上げていただいた。その事例ではカウンセリングを通し、褥婦が実母との関係を良好に築けることになったという展開であった。
【産後の精神障害】
産後の精神障害については、一過性で特に治療の必要性がないマタニティブルーズから、治療を必要とする産後うつ病の概要について説明があった。マタニティブルーズとは出産直後から一週間ごろまでに出現するもので、涙もろさや抑うつ、疲労、不眠などの症状を主とする。出産した女性の5~7割に認められるものであるが、原因としては心理学的・内分泌学的要因が考えられる。対し産後うつ病とは出産後数週間から数ヶ月以内に出現するもので出産後2週間以内に発症することが多いといわれている。症状や概要はうつ病の診断基準に応じるが、特に産後のうつ病には子どもに対するもの、母親としての自己評価の低下を訴える場合が多い。軽症の場合は看護職による傾聴ですむ場合があるが、重症の場合は精神科医による精神療法や薬物療法が必要となる。
【産後うつ病について】
産後うつ病の発症の心理社会モデルと子どもの発達・発達環境との関連についても説明があった。実質的、情緒的援助の不足や愛着スタイルといったリスクにライフイベントである妊娠・出産が加わると産後うつ病を発症しやすい。また育児サポートの欠如があり、育児への対処機能不全があると産後うつ病を発症するリスクと成り得る。また子どもの発達リスクにも関連し、母子相互作用の障害ともなる。これらのリスクはすべて関連性があることが示されている。
【産後うつ病の検査】
出産した女性が産婦人科を退院する前に、うつ病の危険を点検できる迅速な方法としてEPDS(エジンバラ産後うつ病自己評価スケール)がある。EPDSは10項目の自己記入方式設問からなっており、症状の程度に応じて0から3までのスコアをつけるものである。日本における区分点は8~9点であるが8人に1人は9点以上となるという調査実態がある。EPDSからスクリーニングした女性をピックアップして新生児訪問や面接、電話相談、継続的な家庭訪問といった関わりによりフォロー対象者が減り、最終的な精神科受診が必要なケースはほんのわずかとなったという調査結果についても説明があった。
【産後うつ病の対処】
産後うつ病が疑われたら、あわてず、地域助産師、市町村センターの保健師等に相談をするという窓口の紹介、殆どはカウンセリング・仲間との会話で落ち着く、話すことで気持ちが楽になっていくことについての説明がされた。先生はまとめとして「産後のメンタルヘルスケアにおけるドォーラの役割」を強調された。母親に赤ん坊が生まれると、母親の心は生涯の初期に帰り多くの記憶が蘇ってくる。これらの記憶によって、母親の中に、ケアされたい、守られたいという特別なニーズが呼び起こされてくる。この心理的な退行現象の一部として、母親は安全と感じたい、抱かれてケアを受けたいという気持ちが生まれるというものであった。またこのニーズが満たされていないと母親は、見捨てられ一人ぼっちになったと感じ不安になってくる。これは、母親だけでなく父親も同じニーズを持っている。支援者がいると母親も父親も安全を感じることができ、さらに父親は責任の重さから開放されると、産後のメンタルヘルスケアにおける支援者の役割を示唆していただいた。
【講演会】3/4(土)「見えない!子どもの貧困のリアル」
【講演会】出産・子育てをキャリアにするという生き方
満員御礼!ありがとうございました!!
【講演会】出産・子育てから広がる「わたし」の生き方
6/2(月) 講演会「出産・子育てをキャリアにするという生き方」
静岡新聞で紹介されました!「袰岩奈々さん講演会」
【講演会】出産・子育てをキャリアにするという生き方
満員御礼!ありがとうございました!!
【講演会】出産・子育てから広がる「わたし」の生き方
6/2(月) 講演会「出産・子育てをキャリアにするという生き方」
静岡新聞で紹介されました!「袰岩奈々さん講演会」
Posted by mamabuddy at 04:21│Comments(0)
│子育て講演会